2008年11月23日 釈迦ヶ岳、猫岳、金山、水晶岳(鈴鹿)
■釈迦ヶ岳1092m、猫岳1058m、金山906m、水晶岳954m(鈴鹿)2008年11月23日No.471隊長
朝明渓谷駐車場(8:20)〜(9:30)庵座の滝(9:50)〜(11:30)松尾尾根の頭(11:45)〜釈迦ヶ岳1092m(11:52)〜猫岳1058m(12:17)〜白滝分岐(13:06)〜羽鳥峰(13:20)〜金山906m(13:45)〜中峠(14:05)〜水晶岳954m(14:23)〜根の平峠(14:50)〜朝明渓谷駐車場(15:45) 累積標高 +970m 歩行距離11km しっかりと歩いたつもりだが、先週の白山と比べると行程的には3分の2程度だった。
| ページ1 | ページ2 |
シロヤシオの多い笹に道を一旦下って、猫岳へ登り返す。振り返ると大影のガレがよく見える。雪化粧と青空のキャンバスがあれは絵になるのだが。そう思うと積雪期のルートはどうしようか、と考え初めていた。たぶん積雪期に来るだろう。
釈迦ヶ岳はいくつものピークを持つ山塊とみれば猫岳もその一つだろう。大陰のガレとは対照的に円錐形のきれいな形をしている。笹と灌木に包まれた山頂だが岩の上に乗るとある程度見通しが効く。ここからは羽鳥峰へ向けた徐々に高度を下げていく。よく踏まれた稜線は、展望もよく歩きやすい。シロヤシオの老木やらブナに興味を引かれ、花も緑もない季節だが興味深く歩くことができた。猫だけ手前で単独登山者と行き交っただけだった。
白滝谷出会いを過ぎると羽鳥峰峠は近い。朝明への林道コースを見送り樹林を抜けると、風化した花崗岩の岩山に出る。明るく開放的で、頂に立つと展望が開ける。山頂には登山者が一人いた。さてこのまま南下して根の平かで行くか迷ったが、伊勢谷の様子も見ておきたかったし、稜線もしばらく歩いていなかったので、根の平峠まで足を延ばすことした。この間は金山と水晶のピークが二つあるが、それほどの起伏もなく、1時間ちょっとあれば歩けるだろう。
羽鳥峰を後にし、金山へ向けてひとつ標高点のあるピークを乗越し、徐々に高度を取り戻していく。この間の稜線はみえけん側に開けているのでなかなかの好展望だ。朝明渓谷の地形が手に取るように分かる。急斜面の三重県側にあってはかなり深い渓谷であることが分かる。花の季節にはどうしても、御在所や藤原を中心に歩いてしまうのでこの辺りが手薄になってしまっている。来年は是非ともシロヤシオの季節に歩いてみたいと思った。金山は展望のいい山頂だ。午後から歩いてきた縦走路と釈迦ヶ岳が一望でき、この辺り一帯のパノラマが楽しめる。三重県側とは対照的に滋賀県側の山深さがよく分かる。それぞれの季節に、ここからの風景を撮影してみたい。まずは樹氷ねらいだろう。
金山を下ったところが中峠だ。よく利用する峠で、ルートになる伏木谷の様子も確認したいが、まずはメインルートの伊勢谷の様子を見ておきたかったので、今回はパスした。水晶岳へは今日最後の登りになる。この区間もしばらくぶりだ。山頂が近づくと賑やかな話し声が聞こえてきた。犬を連れた家族と年配の男性二人組が山頂を後にするところだった。稜線では今日は誰にも会わないかと思ったが、意に反して水晶は賑やかだった。山頂にあるダムの雨量観測施設も以前と変わりなかった。
風が出て肌寒くなってきたので、山頂を早々に引き上げ根の平峠に降りた。落ち葉を敷き詰めた二次林が明るくきれいだ。平地もありテントサイトには好都合だが、登山口から1時間ほどなので、縦走時以外の利用価値は見つからないだろう。愛知川の方から二人、登山者が帰ってきた。峠から少し下ったところで単独女性を追い越した。この辺りも土石の災害で明るく広くなっている。苔むした石畳の街道の面影もなくなっている。登山道に覆い被さる笹も枯れていて、ブナ清水への分岐も容易に分かるようになってきている。もう少し下ると上部の堰堤が土石で埋まり、護岸の石積みが意味をなさなくなっていた。しかし難所はなく、登山道としては以前と同じように使えるだろう。途中で山頂で出会った家族ずれを追い越し朝明に降りた。紅葉が見頃であった。
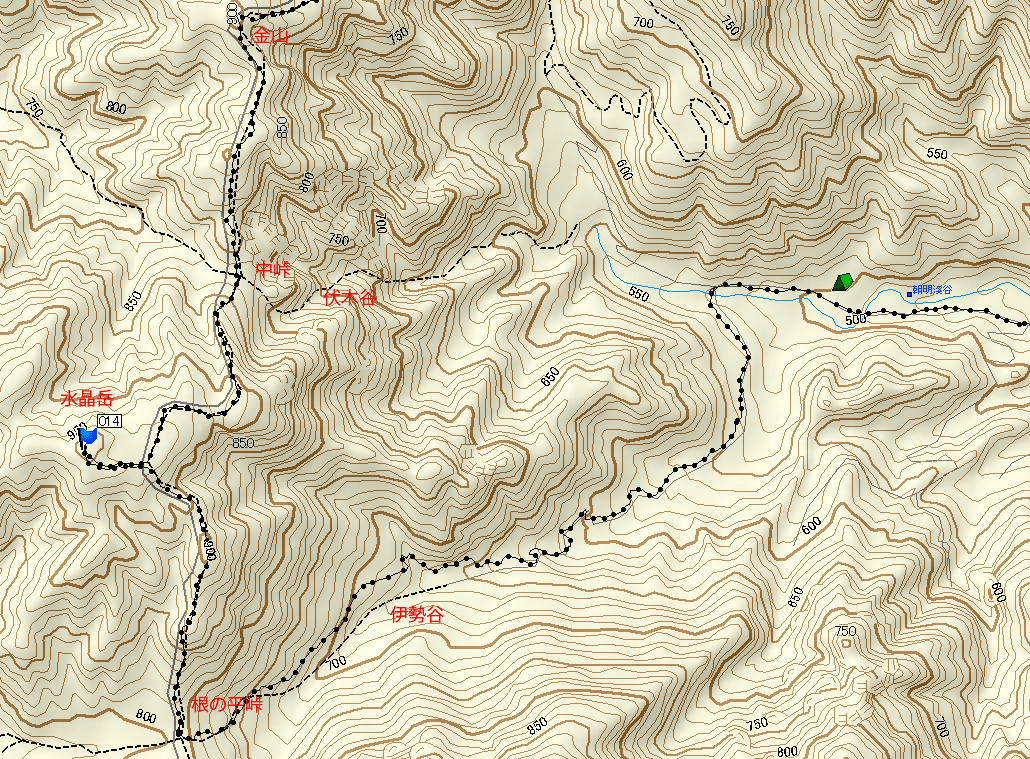
JapanTOPO-10M(日本地形図10m等高線)より引用
軌跡はGARMIN etrecVISTAHCxによる
| ページ1 | ページ2 |
2008年11月23日 Copyright (C) 2008k.kanamaru. All Rights Reserved. home

















